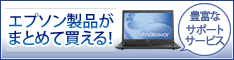- HOME |
- 製品レビュー |
- LCD用語解説 |
- 地デジPC |
- デジタル家電の情報ブログ「インテリジェント・ノート」
EIZO FlexScan EV3237-BK
FlexScanシリーズ初の4Kモデル(UHD:3840×2160)となる、31.5型ワイド液晶モニター
4K解像度(3840x2160:UHD)ディスプレイ
フルHDの4倍!次世代規格ウルトラハイビジョン4Kとは

横の画面解像度が約4,000のものを1,000を表すキロをつけて4K(よんけい)と呼んでいます。
今では一般的になったFHD(フルエイチディー)1920x1080の縦に2倍、横に2倍の2x2で4倍の画面解像度を持っています。QFHD(クアッドフルエイチディー)とも呼ばれます。
スマホやノートPCでも当たり前になったFHD。テレビなども標準的なものはFHDです。しかし4Kのテレビやディスプレイもかなり安くなっており今が買いどきかもしれません。
4Kの基礎知識
超高精細 Ultra HD
映像を作り出す画素数が横に約4000あるものを4(よん)に1000を表すK(けー)をつけて4K(よんけー)と呼ばれています。具体的には3820x2160の解像度を持つ液晶テレビやパソコン用の液晶ディスプレイが4Kテレビ、4Kディスプレイ(モニター)と呼ばれています。
この画素はRGB(赤、緑、青)の色情報を持ったピクセルという点の単位で、横3820x縦2160ピクセルで合計8,294,400ピクセル(約830万画素)のものが4Kになります。フルHDが横1920x縦1080の2,073,600(約200万画素)なので約4倍という高精細な映像を実現します。
画面が同じ大きさならより精細な画素は細かな色や形の表現、滑らかな線の表現、表示できる情報量の拡大などがメリットとして言えます。逆に言えばフルHDの映像が粗っぽく線がカクカクしていて表示できる領域が狭いとなります。
画素数が多いということはメリットです。より綺麗な映像を表現することが可能になります。パソコンなどでも解像度の高い液晶ディスプレイが選択肢に入るようになってきました。
中身という意味ではコンテンツはまだまだですが、スカパーやNetflix、ひかりTV、Youtubeなどでも4Kコンテンツは視聴できますし、ソニーやパナソニックも力を入れているようなのでこれから普及は進むでしょう。
液晶ディスプレイの基礎知識と概要!
LCD:光のシャッターが映し出す映像
液晶:liquid crystal(えきしょう:リキュード クリスタル)とは・・・
液晶とは液体と結晶の形態を併せ持つ物質の状態である。英語で「liquid crystal(リキュード クリスタル)」液体・流動体の結晶である。液晶という物質があるわけではなく「固体」「液体」「気体」などと並ぶ物質の状態である。バックライトの光をシャッターやブラインドのように透過率を調整することで映像を制御することができる。電卓や携帯電話などにも使用されるほか、カーナビやデジカメにも使われる。
液晶ディスプレイ(LCD:liquid crystal display)とは・・・
省スペースと省エネを実現したパソコン用のモニターで、主な出力装置の一つである。大画面化と低価格化が進み、高機能化・高精細な画質など注目される製品です。サイト内では製品ラインナップ&レビューや用語解説などを行います。
液晶テレビとは別のカテゴリー製品で一般にはチューナーやスピーカーを搭載していない映像出力のみを行う機器です。デスクトップ型のパソコンに接続されて使用される。中にはテレビチューナーやスピーカーを搭載するものもあり、一台で二役をこなすものもある。
一般的なテレビより高精細であることなどテレビとの違いがあり、選ぶ際には注意が必要である。パソコン用のモニターとしては、ハイビジョンテレビなども接続用のインターフェースを搭載していることがあり、両者の違いが曖昧な一面もある。
また高解像度の映像出力対応ゲーム機(Xbox360、PS3など)の720p/1080p等のモニターとしても使用されることが増えている。
液晶モニタ・液晶ディスプレイの選び方
画面のサイズと縦横比
【V型】インチ:inch(ビジュアルサイズ)とは・・・
画面の端から端までのナナメの長さです。左下から右上もしくは左上から右下またはその逆を結んだ直線が大きさの表記つまり対角線が大きさの単位です。 インチは約2.54cm
縦横比(アスペクト比またはアスペクト・レシオ[Aspect Ratio])
画面の縦と横の比率。地上波テレビ放送と同じスクエアタイプの4:3や、横長のワイドタイプの16:9などが一般的であるが、パソコン用のモニターは普通16:10で縦に少し長い。ゲーム機の出力に合わせて画面サイズを16:9にしてあるものや、映像を引き伸ばしたり余白を意図的に加えることで映像サイズの調整を行えるものがある。
駆動方式や光沢の有無
「TN・VA・IPS」3つの駆動方式による違い
制御方法には大きく別けて3つの方式があり、TN方式 VA方式 IPS方式のことを指しています。それは液晶パネルの根本的な違いであり、性能に大きく影響します。
TN方式は安価であるが、斜めから見ると映像が変化する視野角の狭さが欠点である。VA方式は視野角が広く、コントラストも高いが少し割高。IPS方式は視野角が最も広く医療用にも使われるが、価格が高く応答速度も遅い。
光沢液晶(グレア)と非光沢液晶(ノングレア)
表面の違いによって2つに分けることができ、光沢のあるグレアはギラギラした質感で、映像が綺麗に見えるが周囲の様子が映りこみ、長時間の作業には向かないとされる。対して光沢のないノングレアはうつりこみがなく目の負担が軽いとされる。
選ぶ基準や購入の決め手
薄くて軽いディスプレイ。
CRTからの絶対優位性
基本的に本体が薄くて軽くどこにでも自由における省スペース性が高く評価された液晶ディスプレイですが、画質の面からは必ずしもいいと思われてはいませんでした。しかし画質の改善が進み、価格も安価になってから標準のディスプレイとして大きなシェアを持っています。
丸みを帯び映りこみが激しいブラウン管と違い、フラットな画面で反射もなくクリアな視界が実現します。目にも優しく負担が少ないため、長時間の作業に適していると言います。
高精細で大画面
一つの大きな特長は大画面化が進み、それに伴って高解像度の高精細になったことです。ワイドな画面で作業性が向上しただけでなく、表示できる情報量や詳細な画像を描画できるため、高画質にデジカメで撮った画像や録画した映像を楽しむことができます。
ワイドの大画面で高解像度の製品をできるだけ選びたいところです。省スペースなので複数のモニターを同時に接続する「マルチディスプレイ」環境を構築するのも面白いかもしれません。
カタログスペック解説
解像度:resolution(かいぞうど:レゾリューション)とは
画面の細かさを表す尺度。液晶ディスプレイではドットの数を表す、標準的なディスプレイはXGAと呼ばれる1024×768の解像度を持っている。1920×1080ピクセル相当の1080iをフルHD(High Definition)フルエイチディーと呼ぶ。
視野角とは:Angle Of Field(しやかく:アングルオブフィールド)
画面を正面から上下左右に移動したとき一定以上のコントラスト比を表示できる角度。パネルによって左右され、TN方式なら160度と狭く、VA方式やIPS方式は170度以上と広いのが特徴。
輝度とは:Brightness(きど:ブライトネス)
コントラスト比とは:contrast
輝度とは画面の明るさのことでcd/m2(カンデラ)で示します。コントラスト比とは最も明るい時と、最も暗い時の輝度の比率で「250:1」など比率で示します。コントラスト比は最も輝度の高い「白」が左側で最も輝度の低い「黒」が右側になります。あくまで比率でコントラスト比が高くても輝度が高いことにはなりません。
応答速度:response speed(おうとうそくど:レスポンス・スピード)
応答速度とは液晶の表示を変化させるのに掛かる時間です。カタログでは黒→白→黒と変化するのに必要な時間をms(ミリセコンド/1000分の1秒)で示します。そのほかにも黒と白の中間の色の表現である中間階調から中間階調への変化(Glay to Glay)があります。黒と白の変化より中間階調の変化の方がよく使用されるのにスペックが公表されていないことが多い。
最大表示色とは:maximum display color
(さいだいひょうじしょく:マキシマム・ディスプレイ・カラー)
ディスプレイが表現することの出来る色の数。RGB各色が8bitの256階調で1677万色をフルカラーと呼ぶ。コンピュータがデータを扱いやすいように24bitではなくダミーデータなどを8bit追加した32bitで表現することが多い。ディザリングなどで誤魔化す26万色しか表現できない「疑似フルカラー」も存在します。
基礎用語解説
LCDパネルとは
liquid crystal display panel
液晶ディスプレイの表示部分。ディスプレイの核となる部分で他には本体を支えるスタンド部分やパソコンとつないだり他のAV機器とつなぐための端子などのインターフェース部分があり全体で一つの製品。
480i 解像度[525i]
有効走査線数480本飛び越し走査(インターレース)方式
テレビ放送の映像信号形式の一つ。有効走査線数480本の飛び越し走査方式で、総走査線数525本、フレーム周波数29.97Hzの映像。画素数は720×480または640×480。現行のアナログテレビ放送と同等のSDTVの映像形式。「i」はインターレースのことで、飛び越し走査とも呼ばれ、奇数列と偶数列を交互に映像を表示していくものです。
液晶ディスプレイ製品ラインナップ
デル デジタルハイエンドシリーズ
3008WFP
2007/12/20発売 30インチワイド液晶モニタ。2560×1600(WQXGA)の高解像度に3000:1の高コントラスト、高い拡張性を備えたフラッグシップモデルです。
EIZO ワイドハイグレード
FlexScan SX2462W ブラック
Adobe RGBカバー率98%、低色度変位のIPSパネル搭載。色ムラ補正など独自の高画質化技術を搭載したFlexScanハイエンドモニター。