- HOME |
- 製品レビュー |
- LCD用語解説 |
- デジタル家電の情報ブログ「インテリジェント・ノート」
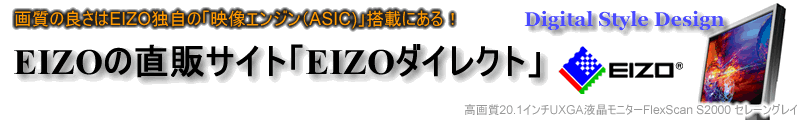
製品選びの基準で「性能」というのは外せない要素ですよね。使い捨てのように耐久性がなく壊れやすかったり、使い勝手が悪かったり、品質が悪いと、いくら安い製品でも少しの金額を払ったことに後悔しますよね。かといって値段が高ければ性能がいいというのは一概には言えません。
技術が未成熟な状態で製品化されたものは一般に価格が高く、その後に急激に安くなったり、性能が飛躍的に向上する可能性があります。いずれの場合も性能に対する価値が、性能に対する値段と釣り合っていないと言えます。
けれども性能で全ての価値を決めることは難しいのではないか、確かにそれは一理あります。製品を求めている時の状況にもよりますし販売側の事情にも関係します。性能以外で価値が決められていることはすでにわかっていることです。でもやっぱり「性能」ははずせない要素ですよね。横一線に製品が並んだ時、性能で選びませんか。「この製品には他の製品にはない機能がある」とか、「少し高いがそれ以上に優れている」とか言われれば選びたくなりますよね。
液晶ディスプレイの性能には主にサイズ、解像度、輝度・コントラスト、応答速度といった共通の基本スペックがあり、ほかにもピボット機能、テレビチューナー内臓、スピーカー内臓など付加機能があります。トータルで考えた場合の性能は、価格に見合っているのでしょうか。以下で一つ一つ解説していきます。
関連用語:FPD 高精細 解像度 有効走査線数
ほとんどのテレビやPC用のモニターは、平面で薄型のフラットパネルディスプレイが主流になっています。消費電力も少なく、室内の空間を有効に使う省スペース設計の薄型ディスプレイは大変人気です。その中でも人気は大画面に集中しています。次から次に大きな製品がリリースされ、価格もどんどん落ちています。
1インチあたりの価格もかなり安くなってきたため、少し予算を高く見積もってワンランク上のワンサイズ大きなディスプレイを選ぶようになったのかもしれません。やっぱり大きい方が、見やすかったり高精細であることが多いからです。
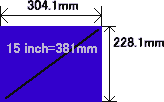
画面のサイズが大きくなり、見やすくて迫力のある映像が得られるのは良いことですが、文字を扱うパソコンでは精細さが重要になってきます。いわゆる画面解像度が鍵を握っているのです。
テレビでは映像を何百本もの横線に分解して表示していますが、この本数が画質に関係する「走査線」の数です。従来のテレビでは525本の走査線を使用して画面に表示される有効走査線数は480本です。ハイビジョンテレビでは、約2倍の1125本を利用し、有効走査線数は1080本になります。
同様の基準で見た場合パソコンでは、「VGA:640x480」の解像度が該当します。しかし現在ではほとんど使用されない低解像度の規格で、液晶ディスプレイの標準的な規格は「XGA:1024x768」です。画面が大きくなるにつれて更に解像度は増し、「SXGA:1280x1024」や「WUXGA:1920x1200」とハイビジョンと同等またはそれ以上になります。
パソコンで扱うのは映像だけではないので、より多くの情報を表示することのできる解像度が必要になります。ハイビジョンテレビでも十分な情報量を表示できますが、「フルHD:1920x1080」同等の高精細なモニターが最適です。
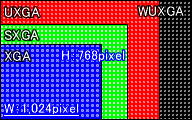
フラットな画面が特徴の液晶ディスプレイですが、致命的ともいえる欠点があります。画素そのものが発光体でない構造の液晶では、映像の見え方に違いが現れます。バックライトの光を調整して明るさや色の変化を実現する構造のため、正面と左右からの斜めの角度や上下の角度の付いた状態だと、意図しない色変化や明るさに異常が見られます。
特に故障していたり不良品というわけでもなく、真横などから覗くと画質が大きく変化してしまうのです。ですがパネルの駆動方式の違いでその変化も違うというもう一つの側面もあります。
比較的安価なTN方式は、液晶がねじれるように駆動するので、正面以外は色の変化や明るさの変化が大きく、上下と左右で視野角が異なる特徴も持ちます。
VA方式は、液晶が垂直に立ち上がるように駆動するので、TNと同じように変化があるのですが、マルチドメインなどの技術を用いて視野角を広くするMVA方式というものもあります。
比較的高価なIPS方式は、液晶が回転するように駆動するので、どの方向にも映像の変化が少なく、かなり広い視野角を持っている。その反面一般的で安価な製品では採用されることはない。
もちろんどんな角度から見ても正常な映像が見られるというのがベストなのですが、正面から見る分にはそれほど気にならない場合も多く、必要以上にこだわることもないと思います。パネルに左右される部分なので、他の部分を見ながら検討すると良いでしょう。
映像を出力する装置「液晶ディスプレイ」では、画質の良し悪しが最も注目すべきスペックです。どんなに安くてもどんなに多機能でも、主要な映像がダメでは評価がグーっと落ちてしまいます。
直接発光するCRTに比べてバックライトによる表示は、暗いとされてきたLCDですが、室内での用途では問題のない明るさを持ち、逆に明るすぎるとされ目への負担も問題視されるのが、ディスプレイの光です。
実際にはカタログ上での輝度の値やコントラスト比の値などスペックは、あまり参考になりません。実物を一目見れば明るさや発色、画質の良し悪しはわかってしまうものなのです。
インターネットを利用して購入することも多くなったパソコン周辺機器ですが、実際に見て触れることのできないオンラインショッピングは、意外と重要な部分を見落としてしまうかもしれません。見ただけでダメだと思うディスプレイは選んではダメなのです。
画面の調整もほとんどすることないでしょうが、輝度といった明るさを調整して、可能な限り暗くすることで目への負担も減りますし、一番の電力消費であるバックライトの消費電力が少なくなることでエコにもつながります。画質との相談で変えてみてはいかがでしょうか。下手にいじってもデフォルトに戻すことができるので、思い切ってやってみるのもいいでしょう。
メーカーにもよりますが、初期不良でもないのに赤色がおかしかったり、色合いが明らかに違うなど発色の違いは当たり前のようにあります。厳密に合わせるのは難しく、広告業界などでは印刷物との誤差を減らすためにカラーマネジメントを用いることもあります。
個人の用途では厳密に色を合わせるような画質の調整は必要ありませんが、こだわるとなると高価な機器とソフトウェアが必要になることもあり、コストパフォーマンスはいいとはいえません。
写真などの静止画とは違い、動画などの動く映像は変化があります。瞬間的な綺麗さだけでなく、刻々と変化する時間の流れをスムーズに表現することが重要なのです。
液晶は発光体ではなく光を制御するシャッターの役割です。バックライトの光をコントロールすることで、色や明るさを調節しています。その切り替えには多少時間がかかってしまいます。
それほど長い時間はかかりませんが、1000分の1秒単位でms(ミリセコンド)を使ってスペックを表現します。電圧がオフの時に黒だとすれば、一番時間のかかるのは電圧が最大の白になるのですが、一度白まで切り替えて、黒に戻るまでに掛かる時間を「応答速度」と呼び、25msなどの時間で表します。
テレビの映像信号は毎秒60フレームで、1フレームあたりの表示時間は約16msであるため、それ以下である必要があった。今では5msや2msといった高速応答の液晶が登場していますが、市場に登場した頃は80msなど遅いものもありました。
黒→白→黒の切り替えは、それほど頻度の多いものではないため、その間の中間階調の表現が重要になります。電圧を途中でとめることで表現する中間部分は、実は切り替えに掛かる時間が遅くなってしまいます。
スペック上は16ms以下であっても、中間階調の応答速度は記載されていないことが多く、それ以上であることも珍しくありません。実際には残像が目立つこともあります。
中間階調の応答速度を改善するオーバードライブ回路などを搭載しており、GtoG(グレートゥーグレー)などの中間階調域での応答速度が表記されているカタログを参考にするのも良いです
2007/12/20発売 30インチワイド液晶モニタ。2560×1600(WQXGA)の高解像度に3000:1の高コントラスト、高い拡張性を備えたフラッグシップモデルです。
Adobe RGBカバー率98%、低色度変位のIPSパネル搭載。色ムラ補正など独自の高画質化技術を搭載したFlexScanハイエンドモニター。