- HOME |
- 製品レビュー |
- LCD用語解説 |
- デジタル家電の情報ブログ「インテリジェント・ノート」
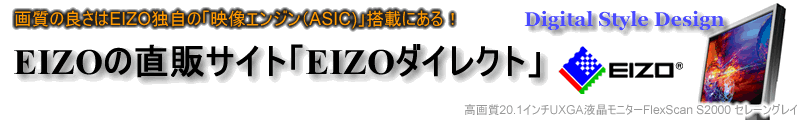
パソコンには音楽を再生するCDプレーヤーや、映画などを再生するDVDプレーヤーなどと同じ、光ディスクを再生できるディスクドライブが搭載されています。CD/DVDのバックアップをパソコンのハードディスク内に行うには、通常リッピングという作業が必要になります。同じくパソコン内のデータからCD/DVDの複製を行うにはライティングという作業が必要になります。
音楽CDなどのデータを吸出したり、変換したりする作業をリッピングと言います。音楽CDは「CD-DA」と呼ばれるデジタル形式の音声データで記録されており、パソコンで扱われるWAVやmp3などのファイル形式ではありません。その為CDをCDドライブへ入れてそのままコピーしようとしても上手くいきません。それはファイル形式で保存することができないからです。そこで変換するソフトが必要となるのです。
記録型のドライブも必要なのかというと、リッピングには必要ありません。読み込みができるドライブなら後はソフトウェアがあれば可能なのです。ソフトウェアの入手方法は、インターネット上からフリーウェアがダウンロードできますし、記録型ドライブを購入すると添付されている場合があります。その他にも多機能な製品ソフトもあるのでチェックしてみてくださいね。
データの吸出しに必要なものはソフトウェアと読み込みが可能なドライブ、そしてデータを抽出する元になるCDです。ただしCDの複製をするのは著作権の侵害にあたる場合があることに注意すること。リッピングソフトのインストールを終えて、ソフトを立ち上げたら、データを抽出するCDをドライブに入れる。リッピングの手順はソフトによって違いがあるので、概要だけを説明しよう。
設定などを行わなくてもCDをドライブに入れると自動で行うソフトもあるだろうが、パソコン内の保存場所くらいは設定する必要がある。あとは「何曲目を複製するか」といったものだ。「どれをどこに保存する」というのはどんな種類のソフトでも共通していることなので、覚えておいてほしい。他にはWAVやmp3などのファイル形式を指定したり、わかりやすいようにファイル名を付けることもできる。
CDのデータをパソコン内に保存しても、同じCDを作成する為には書き込む必要がありますよね。もしパソコンが起動できなくなったり、内部のデータが破損してしまったら元には戻りませんからね。ライティングはリッピングとは違い、物理的にCDへ手を加える必要がありますから、ライティングに対応したドライブが必要になります。それがCD-R・CD-RWドライブです。
Rはレコーダブルで、RWはリライタブルのことである。それぞれ対応したメディアが必要になる。CD-RメディアとCD-RWメディアである。CD-Rは1回の書き込みしかできないが、安価で普通のCD-ROMドライブでほとんど問題なく再生が可能である。一方のCD-RWは書き換えが可能であり、データの消去もできる。価格の方はCD-Rとだいぶ差ができて倍以上はする。また一部のCD-ROMドライブなどでは認識しないなど問題もある。書き換える為に一度データを消去する必要があるため、使い勝手がいいとはいえない。またパケットライトという方式もある。
CDへ音楽データおよびファイルなどを書き込むには、対応したCD-R/RWドライブとCD-R/RWのメディアにライティングソフトが必要なのです。リッピング機能を持ったソフトもありますが、それぞれ別のを使用してもいいと思います。インストール後に立ち上げるというのは、リッピングの時と変わりません。そのほかに書き込むデータの選択と、書き込む速度の選択が必要な作業といえます。
データにはリッピングしたWAVファイルやmp3ファイルを選択し、CD-R/RWメディアの容量に収まるようにしなければなりません。650MBなら74分、700MBなら80分というように時間が決まっています。書き込むデータが決まったらあとはドライブへメディアを入れて、ソフトで書き込みを実行すればいいのですが、複数のドライブがある場合はドライブの選択や、書き込み速度の設定も行うことができます。最高速度などで書き込むと失敗や音飛びの危険があるそうなので、できるだけ遅い速度を選択しましょう。
パソコンは大きく分けると自作派とメーカー製に分類される。自作とはパソコンショップなどで売られている、個々のパーツを選定し、一定の規格内から自分に合ったスペックや価格を設定することである。反対にメーカー製とは、一流の電気メーカーから販売されるモニターから本体、キーボード・マウスといった全てが、独自のデザインで構成されたオリジナルパソコンのことです。
どちらがいいのか。それは個人の好みによると思う。それぞれにいい点がやっぱりあるわけで、一概にどっちが得とか、どっちが損といった比べ方は難しい。それぞれのターゲットとなるマーケットの違いとでも言うのでしょうか。パソコンは常にあなた一人の動向を追っているわけではありませんからね。他の人の選択肢も別に用意されているということです。
初代マイPCが自作だったこともあり、私は自作派です。CPUからマザーボード、グラフィックカードから液晶ディスプレイまで、パソコンに必要なパーツ全てを自分で選んで、自分で組み立てます。もちろんソフトウェアなども付いていませんから、OSからウェブブラウザ、ライティングソフト、セキュリティソフトまで自分で選んでインストールします。
初めは何もわからなかったので、壊してしまわないか心配もあったのですが、慣れてくるとどこを触るのが危険で、どこをイジレば大丈夫なのかを感覚的に理解できます。メーカー製のよさもそれなりにわかるような気がしますし、値段も大分差がなくなってきた気がするので、サポートなどを受けたい方はメーカー製もオススメです。
なんといっても自作PCのよいところは自由にカスタマイズできることでしょうか。メーカー製のPCではあまりパーツの交換だったり、グレードアップしたりすることは少ないでしょうが、自作なら当たり前です。メモリの追加は普通にできますし、ハードディスクの追加も簡単でしょう。ドライブの追加や交換だって問題なくできますし、電源の容量を上げたり、グラフィックカードの交換、2枚挿しなんてのも可能です。
一番重要なのは、それを前提に考えられていて問題なく行えるという点です。メーカー製はパーツの交換などはあまり盛んには行われませんが、自作だとどんなパーツとどんなパーツで構成されるかはわかりませんから、ほとんどの場合は問題なくできるように作られています。最も楽しいと思われるのは、パーツ選びだと思っています。自分が欲しいスペックを自由に選んで組み合わせることができるというのは、メーカー製にはない楽しみです。
パソコンショップに行けば電気店とは違い、パソコンはパーツごとに売られています。ノート型のPCなどは組みあがった状態で売られていますが、デスクトップ型は展示品以外はジャンルごとに分けられています。知らない人から見ると何が置いてあって、何が重要なのかを知る術がありませんからとりあえず値段だけで判断することになるでしょう。その前に何が必要なのかも知らないということが多いはずですが・・・
別に初心者の方でも難しいことはありません。店員さんが全部教えてくれますし、希望を言えば見積もりも出してくれます。価格もメーカー製に比べれば割安だと思いますので、ぜひ買い替えの際は挑戦してもらいたいです。お金があるのなら高いものを揃えるだけで、数年先の標準的なパソコンの性能になるのは間違いないですが・・・逆に言えばそこそこのパソコンでも数年立つと安物と変わらないくらいになります。
私もそろそろ買い換えたいと思っているところですが、2台は必要ない気もしないでもないので踏み切れずにいます。性能は十分なのに最新の性能を見てしまうと欲しくなってしまうのです。上を見るとダメですね。CPUを選ぶならデュアルコアのCore 2 DuoやAthlon64 X2などがいいのですが、格安にするならCeleronを選ぶのも一つの手段かと・・・しかしどうせなら高性能に憧れませんか。
もう一つランクを上げてワークステーションを選ぶのもおもしろい。値段はちょっと違いますが、性能もそこら辺のハイエンドPCと違う。軽自動車一台買うのよりずっと安い気もしますので、快適なデジタルライフを目指すなら見るだけでも損はない。基本的には同じコンピューターですので、最新機種への買い替えをご検討している方は、ぜひネット上でワークステーションを検索してみてはいかがでしょうか。
パソコンでは当たり前のように映画やアニメを見ることが可能になりました。DVDの普及だけでなく、パソコンでのテレビ放送受信や、録画機能といった付加機能もパソコンならではの利点です。見たい場所から一瞬で再生できる便利さや、大容量のハードディスクドライブに保存ができ増設が可能なので、今までよりも管理が楽になったのは言うまでもありません。
動画の種類もテレビ放送は勿論、DVDの映画やアニメ、インターネットを利用したオンラインコンテンツ、ビデオカメラで録画したものまでありとあらゆる動画が楽しめます。もっと行動を広げれば、P2Pソフトを用いて動画コンテンツのファイル共有やライブチャットなどの録画なんてのも可能です。携帯電話のムービー機能や、ライブカメラで撮影した映像の保存・再生が行えます。
パソコンではあらゆる動画の再生が可能だということがわかったでしょうか。いままで動く映像を見るのはテレビだと思っていたのは間違いではありませんが、今はパソコンになったと思います。パソコンには標準で映像を記録する機能はありません。ほとんどの場合はカメラなどの撮影機器を使って撮った映像のデータ保存や、保存された動画のキャプチャーで行います。
保存される形式も、ビデオテープなどのアナログ方式ではなく、AVIやMPEGなど動画ファイルとして保存されます。データ量の多い動画は、ハードディスクの容量を圧迫しますが、DivXというデータを圧縮しながら画質を保つことができるコーデックにより、効率よく保存できます。そんな様々な動画のファイル形式が存在する中で、再生にはパソコンが必要であるというのは大きな問題点です。DVDのメディアに焼いても、通常のDVDプレーヤーでは認識しません。再生にもまたパソコンが必要なのです。
動画ファイルの再生にはWindowsなら標準で付いている「Windows Media Player」が使えます。DVDの再生も可能で、AVI、MPEG、WMVなどの標準的なフォーマットも問題ありません。DivXもコーデックがあれば再生が可能です。その他にもコーデックにはいくつかの種類がありますが、それぞれ専用のプレーヤーかコーデックがあれば再生可能です。
ここで重要なのはコーデックですね。さて何のことかおわかりでしょうか。再生の鍵を握るのはたぶんこの「コーデック:CODEC」だと思います。何がそんなに重要なのでしょうか。コーデックとは「COmpresser DECompressor」のことでデータの圧縮・伸張を行うソフトウェアです。コンプレッサーつまり圧縮するものですが、データを小さくコンパクトにして容量を小さくすることが可能になります。
それだけだとデータは違うものへ変化しもとの情報を持たなくなりますから、データを元へ戻すデコンプレッサーつまり伸張するものとなります。ちなみにデータでは圧縮や解凍・伸張を用いる。立体的に膨らむ膨張とは使わない。一般的なプレーヤーではDivXなどのコーデックを使用しないため、高圧縮された動画の再生は行えない。パソコンではネットでダウンロードすることで簡単に再生が可能となる。
パソコンの一番の利点といえば、膨大な数の動画の管理です。容量はほぼ無制限にファイル形式を問わずに保存が可能で、再生が可能というのは、他のプレーヤーやレコーダーでは敵わないでしょう。ファイルには自由に名前も付けれますし、ハードディスクはコピーや移動も簡単です。外付けのハードディスクなどを利用すれば長期保存も可能で、年代別にテレビ番組をストックすることもできます。ビデオテープのように巻き戻す必要のないのはもちろん、DVDのように毎回取り出す必要もない。高速なアクセスを可能にするハードディスクでは、レスポンスも良く快適です。
パソコンで動画を扱うことが当たり前のようになり、テレビに変わる映像媒体として注目を集める存在ということは紹介しましたが、動画をただ録って溜めるだけがパソコンの使い道ではありません。他の機器にはない編集機能が一番の特長です。さらに容量をおさえつつ高画質で保存ができるエンコードという作業も行うことができます。
動画編集やエンコードといった作業は、高性能なパソコンにとっても大変重い処理で、時間がかかったり処理能力を最大限に使ったり、特別な作業と考えたほうがいいです。動画編集に特化した高性能なパソコンもありますので、作業機会があるのならためしに使ってみるのもいいでしょう。
パソコンは0と1のデジタル情報を使って様々なデータを扱う。単純に2進数を利用した数字だったり、特定のコードで文字を表現したりと様々に意味を持たせ情報を処理してきた。その中でも画像と音声の両方を組み合わせた「動画」は情報量も文字などのテキストや表計算に使う数式などとは、比べ物にならないくらいたくさん使います。その動画を編集するというのはどういうことなのでしょうか。単純に切ったり繋げたりすること以外にも、画質を保ったまま容量を小さくするエンコードとは何なのでしょうか。
エンコードとは符号化のこと。enは接頭辞で他の言葉にくっ付いて意味を変えるものである。codeは符号という意味がある。codeにenが付くことで符号化の意味をなす。パソコンでは0と1のデジタル情報であるが、それを符号化することで容量を小さくできる。動画のエンコードもデータ圧縮の一つといえる。動く画像というのはその前後が似ているものであるから、それを符号で表現することで容量を抑えられる。そんなことを繰り返すのが動画のエンコードである。符号化するとはどんなことなのか。どういう法則でそれが行われるのか。そしてそれを行うパソコンにはどれくらいの性能が求められるのでしょうか。実際のスペックは・・・
データを圧縮する方法や理論はたくさんある。その中身を解説していくと来年になっても終わらない気がするので、概要を説明する。データを圧縮する符号化は、一定のルールで置き変えることだ。私がわかりやすいと思って覚えていたのが、0と1の連続した数を置き換えるというものだ。例えば000111001101なら332211に置き変える事ができ、それを2進数に変えれば圧縮完了というものである。場合によって0と1の数が増えてしまうのは、説明の為に出した例題ということで多めに見てほしい。実際にはそういったルールをアルゴリズムと呼び、それによってデータの圧縮率も違うのである。実際に動画をエンコードするには膨大なデータを処理しなければならない。それには高性能なパソコンが必要になってくるのである。重要なのはCPUの処理能力です。
CPUのスペックで何GHz(なんギガヘルツ)というのを聞いたことはないだろうか。ヘルツとは周波数のことで、波の往復が1秒間に何回あるかを示した言 葉で、1G(いちギガ)なら1×1000の3乗(10の3乗の3乗つまり10の9乗)いちの後ろにゼロが九つあり、1秒間に10億回の振動があるというこ とです。周波数が高いほどCPUは処理能力が高い傾向にありますので、動画編集などで特にエンコードをするなら、高い周波数のCPUを選ぶ必要があります。最新のCPUであるCore 2 Duoでも、DVDと同じ容量を半分くらいに圧縮するには1時間はかかると思う。正確な数字はあまりわからないが、Pen4でも数時間をかけることもある。周波数がGHzに満たなければ、半日や丸一日というのもありえる話だ。その間パソコンをひたすら放置というのは私には我慢ができない。
Athlon64 X2やCore 2 DuoといったCPUのコアが2つあるマルチコアは、処理能力が高いのは想像がつくでしょう。通常のオフィスソフトやネットサーフィンの利用では違いが体感できないと思いますが、動画のエンコードではその違いがよく現れるのです。CPUは常に処理能力を使い切っているわけではありませんから、余裕があるうちは性能の低いCPUでもその違いはあまりありません。しかし処理の重いエンコードなどの作業はフルで性能を発揮しますから、性能の違いがモロに出るというわけです。
もし録り溜めた動画をエンコードしたいと考えているのなら、高性能なマルチコアのCPUをぜひ選んでいただきたい。まだまだ価格は高いですが、それなりの価値はあると思います。この先CPUのコアは更に増え4個8個が当たり前になるかもしれません。そうすると単純に考えれば、20分や10分程度で動画のエンコードができることも現実となるかもしれません。
ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)の個人情報流出が有名になりました。違法なファイルが流通する、無法地帯と化したネットワークだと、ウィルスが蔓延する危険なソフトだと、メディアなどで報じられていた気がします。実際にはそういう一面もあるでしょう。流通するファイルの中には著作権のある映画やアニメ、音楽CDのエンコードされたmp3ファイル、ゲームソフトからDVDのイメージファイルまで、違法性があるのは事実です。
しかしウィルスが蔓延するのは、知識の乏しいビギナーの方が危険性もわからずに違法なファイルを共有しようとするからではありませんか。それがWinnyを代表するファイル共有ソフトの存在価値を、一部で否定しているのではないでしょうか。P2Pソフトは上手に利用すれば、ネットワーク資源を有効に活用できる次世代の情報網の利用法だと思います。このネットワークの発展を、悪意のあるクラッカーの手によって止めてもよいのでしょうか。
まだまだ残された課題も多いP2Pネットワークですが、私たちユーザーの利益の為に発展させていこうではないか。「私は、ネットワーク存亡をかけた最後の防衛策として、P2Pの導入実行を、今ここに宣言いたします!」(笑)
特定のサーバーを介さず、ユーザーとユーザーの間で通信(データのやり取りを含む)ができるのは、P2Pの特長ですが、なぜその一ソフトであるWinnyがこれほどまでに有名なのでしょうか。それはWinnyの名の由来に遡る。ファイル共有の前に行われていたのは、特定の人と特定のファイルをやり取りする「ファイル交換」です。そのソフト名がWinMX(ウィンエムエックス)であり、Winny開発のきっかけになる。
私も詳しくは知らないが、交換という敷居の高さをよく思わなかった2ちゃんねらーが、スレッドの中で開発の議論を交わしていたらしい。その47番目に書き込んだ開発の中心的な人物が、47氏(よんななし)といつしか呼ばれWinnyをつくったのだ。発生がどこかもわからないソフトウェアではなく、ファイル交換という実情の後に生まれたソフトウェアであったことは、話題性もあったのだろう。ユーザー数は増え、認知度も高まった。
それが逆に仇となったのか、セキュリティ意識の低いパソコンビギナーが、無防備のままP2Pネットワークに侵入してきた。それももの凄い数と早さで・・・たちまち悪意のあるユーザーのウィルスは猛威を振るい、何も知らないユーザーは感染していったのだった。それが明らかになったのはずっと後の話だと私は思う。
ウィニーの問題点や流行モノを追いかける人々の論点が、次なるファイル共有P2Pネットワークを望んだ。そこに登場したのが「Share(シェア)」別名シャレである。シェアが共有するという意味なので、各個人のもつファイルを積極的に共有しようという、まったくそのままの名前である。基本的には同じP2Pソフトであり、ウィルスも存在する。実はこれ以外にもP2Pソフトはたくさん存在する。知らない間に個人同士をつなぐネットワークは確実に広まっていたのだ。それは日本だけでなく世界中で・・・
複数存在するP2Pソフトウェアはそれぞれ互換性がないことが、多いというかほとんどだろう。それぞれのネットワークは独立して存在していると考えた方がいい。そしてそれぞれのネットワークで流通しているファイルも、質や量に違いがあることに注目したい。最新作が多いネットワークもあれば、特定のジャンルに強いネットワークもある。
そこでユーザーが出した答えと行動はどういったものだったのでしょうか。互換性のない、異なるネットワークをどのように利用したのでしょうか。もちろん使い分けることにしたんです。複数のP2Pネットワークを使用して、目的のファイルを、より効率的に落とすために同時に使い始めました・・・
複数のP2Pソフトを起動して、複数のP2Pネットワークを利用しても効率は上がらないと私は思っている。実際に試したことはないが、ネットワークのトラフィックを増大させてもファイルの入手効率が上がるわけではないと思う。単独使用していても、時間帯によっては通信が多すぎて、ファイルの転送に帯域を使えないという感じがする。光ファイバーなど高速な通信が可能なら結果は変わるかもしれないが・・・複数起動によってアクセス回数は増えるかもしれないが、それによって転送量を絞ってしまいかねないのではないか。もしファイルをより効率的に集めようとするなら対象を絞る方がいいのではないか。
P2Pの特長なのか、ファイルは転送しやすいように小さく分けられる。更に暗号化も行われるので、分割されたファイルが全て揃うまで元のファイルを生成できない。気が付くとファイルに変換される前のキャッシュが、ハードディスクの容量を圧迫するくらい肥大するのである。それに気付かずにいると、ネットワークの切断や古いキャッシュファイルの削除など、弊害が起こる。ファイル共有が話題となってからHDDなどのストレージ製品が、売上を伸ばしているという。まぁわからないでもない、検索を掛けるとおもしろいほど欲しいファイルが引っかかる。HDDの空き容量など気にする暇もないのだろう・・・
違法なファイルに目がくらんだ偽装ファイルの被害者たち、無知でマナー知らずのパソコン初心者、そんな人たちでもちょっとした知識や利用法を身に付けることで、安全にそして有益にP2Pを使えるのだ。ファイルの拡張子の表示、ウィルス対策ソフトウェア及びファイアウォールの導入、ウィルスに関する最新の情報を入手することは、必須であるといえる。
もちろんどんなに注意していてもパソコンを使用していればウィルス感染の危険はあるだろう。もし感染してしまったら・・・感染に気付くことができたならばどうすればいいのだろうか。それはLANケーブルを引っ張り抜くことである。これは冗談に思えるが重要なことであると言いたい。感染の疑いがある場合に我々がしなければならないことは、2次災害を防ぐことである。
そのために物理的にネットワークから、パソコンを切り離すのである。オフラインになったパソコンにゆっくりとウィルス検知や対策を施して、安全が確認できるまで接続しないことである。これが最も重要で最も簡単な利用法である。あとは高速な回線をひっぱり、処理能力の高いパソコンを組み立て、大容量のHDDを買いあさって、ひたすら待つのである。
2010年5月発売
優れたパフォーマンスと鮮やかな色彩で、WQHD の高解像度なのでスペック十分!驚きのリアルな画像をぜひ体験してください。
Adobe RGBカバー率98%、低色度変位のIPSパネル搭載。色ムラ補正など独自の高画質化技術を搭載したFlexScanハイエンドモニター。